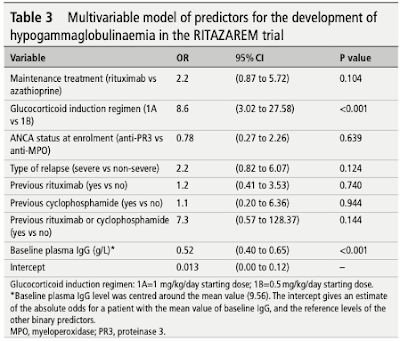症例: 高齢者, 腸管穿孔による腹膜炎, 敗血症で搬送された.
緊急手術となり, 手術自体は問題なく終了. 術後ICU管理となった.
ICU管理2日後, 意識障害と38度台の発熱, 下肢の筋硬直が出現.
顎を確認すると, 開口が困難であった.
さて, 何を考えるか?
というわけで, 表題通り破傷風です.
破傷風はClostridium tetani(破傷風菌)による感染症.
(J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69:292-301)
・嫌気性のGPRであり, 嫌気状態で芽胞化し, Neurotoxinを放出(tetanospasmin, tetanolysin).
下肢の創傷, 産後・中絶後感染症, 不衛生なIM, 解放骨折がRisk.
他にはIM, IV, 鍼灸, ピアス,
中耳炎, 褥瘡からの感染もある
・QuinineのIM後に
発症するものは予後不良
(QuinineはLow pHであり,
神経移行性がUPするため)
・また, 30%で明らかなEntryが見つからない
・潜伏期; 24hr~60dと幅広い.
7-10dが最多.
感染部位, Toxinの性質に由来.
外科手術後の破傷風
・75例の破傷風症例の解析では,
外傷後が40.9%, 皮膚障害が33.8%, 外科手術後が16.9%の頻度(Med Sante Trop. 2019 Aug 1;29(3):333-336.)
・近年は抗菌薬や周術期の衛生管理の発展があり,
およそ0-3.5%が外科手術後の発症
・主な感染源は消化管.
・一般人口の1-10%で糞便よりC. tetaniが検出される.
・腹部外科手術, 腸管壊死症例などで, 術後の破傷風を発症した症例報告がある.
(BMJ Case Rep 2019;12:e229701.)
腹部外科手術後の破傷風の症例 (Surg Today (2012) 42:470–474)
ワクチンが普及したとは言え,
未だ800 000~1 000 000/yrの死亡がある.
(内400 000は新生児例)
死亡率は6-60%
(J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69:292-301)
・死亡例の80%がAfrica, 東南アジア.
先進国でもたまに見られる疾患であり, 注意が必要.
・アメリカでは0.10/100万人口/yrの発症率(2001-2008年).
65歳以上では0.23/100万とリスクは増加.
(大半がワクチン未接種 or 10年以内のブースター無しの群)
・死亡率は13.2%
・破傷風による死亡率は年齢差が大きく,
<30yrではほぼ0%, >60yrでは50%に及ぶ.(破傷風の75%が>60yr)
(Southern Medical Journal 2011;104:613-617)
ワクチンは10年毎のブースターが必要
・小児期にDPTワクチンを行うが,
時間経過と共に効果が消失するため, 10年毎のブースターが推奨
・実際96例の日本人旅行者のAntitoxin levelを評価したStudyでは,
(J Infect Chemother 20 (2014) 35−37)
<40歳ではほぼ全例で
ブースター前から破傷風に対する
免疫は有しているが,
≥40歳では約半数のみしか有さない
ブースターしても100%ではない.
Neurotoxin: Tetanus, Botulinus Toxinは共通部分が多い
(J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75(Suppl III))
・100kDaのHeavy chain, 50kDaのLighter chainを有し,
H鎖は末梢神経末端のGangliosideに結合し, Endocytosisを起こす.
・H鎖は小胞壁に通過性の孔を形成し, L鎖が細胞質内へ侵入する.
・Botulinus, Tetanus ToxinのL鎖はZn Activated Proteaseであり,
Synaptobrevin(VAMP), SNAP-25, Syntaxinに結合, 作用する
・ToxinとTarget Proteins
Toxin | Target |
Tetanus toxin | VAMP |
Botulinum toxin A | SNAP-25 |
B | VAMP |
C | SNAP-25 |
D | VAMP |
E | SNAP-25 |
F | VAMP |
G | VAMP |
・Tetanus, Botulinumも作用部位は同じであり,
分解作用, 伝導の阻害作用を示すが,
一方は強直, 一方は弛緩症状が主.
・Botulinumは末梢神経末端に残存,
・Tetanusは軸索を逆行し, 神経細胞, CNSへ.
中枢を抑制し, 末梢は興奮してしまう
・両方とも自律神経系も同様に作用するが,
Tetanusの方が強く作用, 自律神経障害を認める
破傷風の臨床
・全身性破傷風; 全身の筋硬直, 疼痛, 頭痛, 硬直性発作
局所性破傷風; 感染部位周囲の硬直, 疼痛
・全身性が一般的であるが, 局所性の場合は予後は良好.
・初発症状として, Lock jawが最も多い.
・軽い刺激(音, 触, 光, 注射, 吸引) で硬直発作が誘発されるため,
暗室に入院させ, 出来るだけ刺激を避ける必要がある.
・Spasm ⇒ 喉頭閉鎖, 胸郭の運動低下 ⇒ 肺コンプライアンス低下
, 呼吸停止による死亡例が多い.
(新生児では死亡率65-90% without Ventilator vs 10% with Ventilator)
・Spasmは2wkでピークとなり,
自律神経障害はSpasm発症後 数日~2wkで出現する
交感神経↑ ⇒ 唾液分泌, 頻脈, 高血圧, 下痢と褐色細胞腫Like.
・筋硬直は6-8wkまで持続することもある.
成人例 500名の解析(J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69:292-301)
・Entry Site; 下肢 53.3%, 頭部 10.4%
, 上肢 10.8%, 注射 1.8%
, 不明 22.2%
・潜伏期間; 平均9.5d [1-60]
・初発症状~Spasmまでの期間; 48hr[0-264]
・入院時の症状;
Lock jaw | 96% | Spasm | 41% |
背部痛 | 94% | 発汗 | 10% |
筋硬直 | 94% | 呼吸困難感 | 10% |
Dysphagia | 83% | 発熱 | 7% |
Reviewより, 入院時の症状の頻度 (Lancet 2019;393:1657-1668)
破傷風の診断は臨床診断が決め手となる
(Southern Medical Journal 2011;104:613-617)
・特異的な検査は無く, 創部培養も補助手段程度の診断能しかない
・創部培養は通常陰性. 症例の30%程度でしか菌は検出されない.
・検査は他の疾患の除外目的として行われる.
・鑑別診断として,
Tetany, ストリキニーネ中毒, 薬剤性ジストニア, 狂犬病,
口腔, 顔面感染症, セロトニン症候群, 蜘蛛刺傷など
新生児例では,
低Ca血症, 低血糖, 髄膜炎, 髄膜脳炎, てんかんも重要な鑑別
重症度
破傷風の治療:
(J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69:292-301)
治療は創部のデブリ & 抗生剤で毒素放出の抑制し,
遊離毒素の中和をTetanus immunoglobulinで行う.
・Anti-tetanus Immunoglobulin(テタノブリン); 発症24hr以内に投与.
Doseは小児も成人も500IUを筋注.
500IU IMは3000-10000IU IMと同等の効果を示す.
重症例では1500-5000Uを筋注もしくは緩徐に静脈投与
罹患期間, 重症度の改善効果を示すが,
Anaphylactic reactionが20%で認められる.
カテコラミン, ステロイド, 補液を必要とするものは1%程度
・破傷風トキソイド
Immunoglobulinによる短期的免疫反応に加えて,
トキソイドによる長期的免疫反応を引き起こす.
トキソイドでアレルギーを来すのは1/50 000と稀
しかも大半が疼痛,浮腫,Flu-like illness.
破傷風トキソイドとグロブリンは同じ部位に投与しては×
注射部位で反応を起こしてしまう.
同じ部位に投与する場合は, グロブリンの投与量を調節すべき
抗生剤の1st choiceはMetronidazole
・Metronidazole; 400mg q6hr直腸投与. 7-10d継続
500mg q6hr IV投与. 7-10d継続
・他にはエリスロマイシン, テトラサイクリン, VCM,
クリンダマイシン, ドキシサイクリンなどを使用.
・ペニシリンも有効であるが, てんかん閾値を下げるため避ける
PCのβ-lactam環より遠位部の構造がGABAと似ており,
高濃度で使用すると, CNSにてGABA抑制効果を示す可能性が示唆される
破傷風の中枢性の筋硬直を助長する可能性があり, 避ける.
Metronidazoleによる治療と比較し,
Outcomeは同等であるが, 鎮静, 鎮痛剤の必要量は低下する.
呼吸筋硬直, 喉頭閉鎖による呼吸不全治療, 予防に
挿管, 人工呼吸管理も重要な治療
・PropofolはSpasm, rigidityのコントロールも可能で良い適応.
・鎮静剤としてはベンゾも有用
⇒ 自律神経障害にも有効だが, 半減期が長く,残存する可能性も.
・筋弛緩薬; Pancuronium, Vecuroniumが良く使用される.
自律神経障害
・カテコラミン過剰状態 ≒ 褐色細胞腫の症状と類似.
発汗, 頻脈, 高血圧, 流涎など
・ベンゾジアゼピンやβ, α阻害薬が有効.
・Diazepamは大量に必要となり, 200mgまで増量することも.
その他の治療
・マグネシウム
>15yrの破傷風患者256名のRCT; 硫酸Mg IV群 vs Placebo群で比較
(DB, 7dフォロー) (Lancet 2006;368:1436-43)
Mg; 40mg/kg 30minでLoading
Wt >45kgでは2g/hr, Wt =<45kgでは1.5g/hrで持続.
人工呼吸器使用, 生存率は有意差認めなかったが,
鎮静剤の必要量は有意に低下を認めた.
副作用は有意差無し
・Vit B6, ステロイド