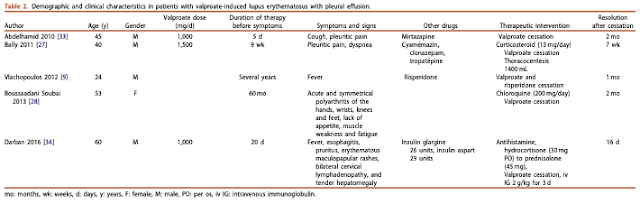中枢神経リンパ腫(CNS lymphoma: 以下CNSL)の診断は難しい.
Gold standardは脳生検であるが, そのハードルは高く, 髄液検査で異常細胞が検出されればよいものの, その細胞診の感度は<50%程度に過ぎない.
また, 髄液量も10.5ml以上採取することが推奨されるため, 意識していないと検体が足りないということも多々ある.
他には髄液のFCM, TCR遺伝子再配列, IgHの評価が有用である.
CNSLの診断に有用な髄液マーカーにはどのようなものがあるだろうか?
国内より, 複数のCSFマーカーを使用したCNS lymphomaの診断能を評価した報告
(Cancer Medicine. 2020;9:4114–4125.)
・髄液中のマーカーでは, CXCL-13, IL-10, β2-MG, sIL-2Rの組み合わせはCNS lymphomaの診断に有用であるとの結論.
・コマーシャルベースで考慮するならば, IL-10, β2-MG, sIL-2Rの組み合わせであるが, CXCL-13がどれも含まれており, そこが難点.
2018年のSystematic reviewより, 髄液マーカーのカットオフや分布, 感度特異度を評価したものをまとめる. (British Journal of Haematology, 2018, 182, 384–403)
髄液中IL-10
・IL-10は悪性リンパ腫細胞や腫瘍内に浸潤しているMφからも産生, 分泌されている.
対象群 | Cutoff | CNS L群の中央, 平均値 | SN | SP | |
Mabray (2016) | 転移性腫瘍, Glioma, 脱髄性病態 | >21.77pg/mL | 557.5pg/mL(167.5-947.5) | 62.8% | 95.5% |
Nguyen-Them(2016) | Glioma, Ependymoma, Medulloblastoma, 転移, 神経炎症性疾患 | >4pg/mL | - | 88.6% | 88.9% |
Song(2016) | NHL, 中枢神経炎症性疾患, 感染症, 脱髄性疾患, 他の脳腫瘍 | >8.2pg/mL | 74.7pg/mL(<5.0-1000) | 95.5% | 96.1% |
Sasagawa(2015) | Glioblastoma, Astrocytoma, Glioma, Ependymoma, 転移, 他腫瘍, MSなど | >3pg/mL | 28pg/mL(≤2-4100) | 94.7% | 100% |
Rubenstein(2013) | 神経炎症性疾患, 原発性脳腫瘍, 転移 | >16.15pg/mL | *別記載 | 65.4% | 92.6% |
Rubenstein(2013) | 神経炎症性疾患, 原発性脳腫瘍, 転移 | >23pg/mL | *別記載 | 64% | 94% |
Sasayama(2012) | 他のCNS腫瘍, CNS炎症 | 9.5pg/mL | 27pg/mL(<2-1610) | 71% | 100% |
・各病態ごとのIL-10値の分布
患者群 疾患 | IL-10 | 対象群 疾患 | IL-10 |
PCNSL 新規診断(43) | 282.9±113pg/mL | 神経炎症性疾患(71) | 5.6±2.3 |
SCNSL 新規診断(43) | 57±37pg/mL | 原発性脳腫瘍(8) | 10.9±5.6 |
PCNSL 再発例(17) | 1663±483pg/mL | 脳転移性腫瘍(12) | 5.3±1.5 |
SCNSL 再発例(13) | 302±126pg/mL | CNS外の感染症, 腫瘍(46) | 3.6±1.4 |
・CNSLでは大きくIL-10は上昇する. 一方で炎症性の病態でのIL-10の上昇は乏しい.
髄液中IL-6とIL-10/IL-6比
対象群 | Cutoff | CNS L群の中央, 平均値 | SN | SP | |
Song(2016) | NHL, 中枢神経炎症性疾患, 感染症, 脱髄性疾患, 他の脳腫瘍 | >5.1pg/mL | 5.2pg/mL(<2.0-109) | 54.6% | 70.1% |
>0.72 | 12.6(0-115) | 95.6% | 100% | ||
Sasagawa(2015) | Glioblastoma, Astrocytoma, Glioma, Ependymoma, 転移, 他腫瘍, MSなど | >2.2 | 10.8pg/mL(1.2-127) | 68.4% | 96.1% |
Sasayama(2012) | 他のCNS腫瘍, CNS炎症 | 4.0pg/mL | 5.7pg/mL(1.2-264) | 77% | 63% |
・CSF-IL-6はCNSLと他の病態との鑑別には有用とは言い難い.
IL-10/IL-6比も試されているが, IL-10のみで十分ともとれる.
髄液中CXCL-13
・CXCL-13はケモカインの1つであり, 樹状細胞より産生される.
対象群 | Cutoff | CNS L群の中央, 平均値 | SN | SP | |
Mabray (2016) | 転移性腫瘍, Glioma, 脱髄性病態 | >103.0pg/mL | 2960.5pg/mL(1125-4796) | 76.7% | 90.9% |
Rubenstein(2013) | 神経炎症性疾患, 原発性脳腫瘍, 転移 | >90pg/mL | *別記載 | 69.9% | 92.7% |
Rubenstein(2013) | 神経炎症性疾患, 原発性脳腫瘍, 転移 | >116pg/mL | *別記載 | 71% | 95% |
・各病態における分布
患者群 疾患 | CXCL13 | 対象群 疾患 | CXCL13 |
PCNSL 新規診断(43) | 5926±2030pg/mL | 神経炎症性疾患(71) | 44.9±19 |
SCNSL 新規診断(43) | 1783±896pg/mL | 原発性脳腫瘍(8) | 84.5±60.7 |
PCNSL 再発例(17) | 996±312pg/mL | 脳転移性腫瘍(12) | 58.5±41.6 |
SCNSL 再発例(13) | 539±157pg/mL | CNS外の感染症, 腫瘍(46) | 11±3.6 |
・これもCNSLでは他の病態と比較して桁違いに上昇する
他のマーカー
CSF-IL-2Rのまとめ
対象群 | Cutoff | CNS L群の中央, 平均値 | SN | SP | |
Sasagawa(2015) | Glioblastoma, Astrocytoma, Glioma, Ependymoma, 転移, 他腫瘍, MSなど | >60.4 U/mL | 225 U/mL(<54.5-2750) | 94.7% | 84.6% |
Sasayama(2012) | 他のCNS腫瘍, CNS炎症 | 77 U/mL | 100 U/mL(<50-978) | 81% | 83.3% |
・報告はさほど多くないが, 感度, 特異度は良好. 対象群として炎症性病態は少ないため, その点注意が必要である
・Sasayama(2012)におけるCNS炎症性病態は2例のみ
β2MGのまとめ
対象群 | Cutoff | CNS L群の中央, 平均値 | SN | SP | |
Sasagawa(2015) | Glioblastoma, Astrocytoma, Glioma, Ependymoma, 転移, 他腫瘍, MSなど | >2.4mg/L | 3.9mg/L(1.7-11.8) | 89.4% | 88.5% |
Sasayama(2012) | 他のCNS腫瘍, CNS炎症 | 2056µg/L | 4084µg/L(970-11239) | 88% | 90.3% |
Muniz(2014) | DLBCL, BLでCNS病変無し | >2.56ng/mL | 62% | 90% | |
Kerstein(1996) | NHL, ALLでCNS病変なし | >1.67mg/L | 81% | 68% | |
Ernerudh(1987) | NHL, HDでCNS病変なし | >1.9mg/L | 3.9±3.4mg/L | 71% | 67% |
・古い論文が比較的多い. またこれも炎症性の病態との対比がすくないため注意.
Sasayama(2012)におけるCNS炎症性病態は2例のみ
---------------------------------
CNSリンパ腫を疑う際に参考となるCSFマーカーとしては,
IL-10, CXCL13は有用であろう. これらは他腫瘍や炎症性の病態, 脱髄性の病態との鑑別でも有用と考えられる. しかしながらCXCL13はコマーシャルベースでは評価不可.
他にIL-2Rやβ2-MGも利用可能であるが, 炎症性の病態との鑑別は不十分である.