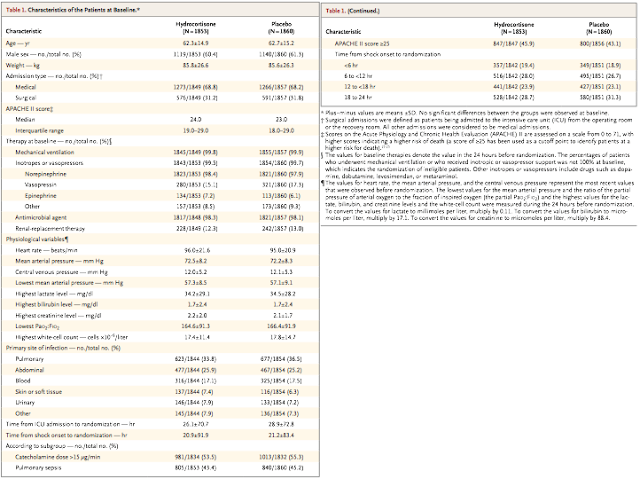炎症反応高値, 腎不全・無菌性膿尿・顆粒円柱など, LPにてCSF細胞増多(若干Neu有意), CSF-prot上昇などあり.
各種培養陰性, 薬剤中止後の炎症反応改善, 腎機能改善・・・などなどから,
おそらくは薬剤性無菌性髄膜炎の可能性を考慮 という架空の症例
--------------------------------
薬剤性無菌性髄膜炎: Drug-Induced Aseptic Meningitis(DIAM)
(Arch Intern Med 1999;159:1185-94)
(Drug-induced aseptic meningitis: a mini-review. Fundamental & Clinical Pharmacology 2018)
薬剤の直接的な髄膜の障害(髄注)と, 免疫機序の髄膜炎がある
無菌性髄膜炎を来す薬剤で有名なものは,
・NSAID, 抗生剤, IVIG, OKT3 monoclonal antibody
抗生剤では, ST合剤, INH, PZA, Ciprofloxacin, PC, Metronidazole, Cephalosporin, Sulfisoxazoleで報告例あり.
NSAIDは最も報告が多く, イブプロフェンが有名. 背景にSLEなどの自己免疫疾患を持つ症例でリスクが高い.
・他にはワクチンやモノクローナル抗体でも報告あり
・平均年齢は20-40台であり,
内服~発症までの期間は様々で10min~10hr, 1wk~4moと幅広い
DIAMの症状頻度
症状
|
頻度
|
症状
|
頻度
|
症状
|
頻度
|
発熱
|
86%
|
関節痛, 筋肉痛
|
54%
|
乳頭浮腫
|
6%
|
頭痛
|
79%
|
低血圧
|
9%
|
リンパ節腫大
|
9%
|
髄膜刺激症状
|
70%
|
顔面浮腫
|
24%
|
肝の異常
|
10%
|
悪心, 嘔吐
|
53%
|
意識障害
|
50%
|
光過敏
|
32%
|
皮疹
|
12%
|
神経局所症状
|
18%
|
||
腹痛
|
9%
|
痙攣
|
10%
|
(JAMA Intern Med. 2014 Sep;174(9):1511-2.)
・原因薬剤は4タイプに分類される.
NSAID, 抗生剤, 免疫抑制剤, 抗てんかん薬.
SLEを基礎にもつ患者では特にリスクが高い.
原因薬剤と症状の頻度
NSAIDs
|
抗生剤
|
免疫抑制剤
|
SLE
|
全体
|
|
発熱
|
91%
|
88%
|
72%
|
88%
|
88%
|
頭痛
|
81%
|
84%
|
83%
|
83%
|
82%
|
髄膜症状
|
73%
|
71%
|
67%
|
75%
|
72%
|
悪心, 嘔吐
|
60%
|
49%
|
11%
|
67%
|
49%
|
皮疹
|
16%
|
11%
|
11%
|
30%
|
13%
|
腹痛
|
6%
|
6%
|
6%
|
17%
|
5%
|
関節, 筋痛
|
16%
|
13%
|
17%
|
25%
|
15%
|
低血圧
|
15%
|
3%
|
6%
|
29%
|
9%
|
顔面浮腫
|
16%
|
16%
|
6%
|
17%
|
14%
|
意識障害
|
49%
|
55%
|
11%
|
58%
|
47%
|
神経局所症状
|
10%
|
7%
|
NA
|
9%
|
10%
|
痙攣
|
4%
|
7%
|
NA
|
9%
|
5%
|
乳頭浮腫
|
5%
|
6%
|
NA
|
8%
|
5%
|
リンパ節腫大
|
3%
|
7%
|
NA
|
4%
|
4%
|
肝酵素異常
|
5%
|
11%
|
22%
|
12%
|
11%
|
羞明
|
9%
|
11%
|
16%
|
12%
|
11%
|
聴覚過敏
|
NA
|
2%
|
11%
|
NA
|
2%
|
NSAIDによるDIAM
・最も多く報告されている薬剤がNSAID.
特にイブプロフェンで多く, 他はジクロフェナク, ナプロキセン, スリンダクなど.
SLEやシェーグレン症候群, MCTDがあるとさらにリスクが上昇する
イブプロフェンによるDIAMのLiterature review
(Medicine 2006;85:214–220)
・36例の患者より71エピソードのDIAM. 22例は再投与で再発を認めた.
女性が64%, 年齢は41歳[21-74]
61%は背景に自己免疫疾患あり(SLE 39%, MCTD 16.6%, RA 2.8%, SS)
・内服~発症までは様々だが, 時間が判明した46件中36例は<24h
・症状は発熱, 意識障害, 頭痛, 項部硬直, 悪心嘔吐など.
髄液所見
・CSF圧は正常~上昇まで様々
・CSF細胞数は280[9-5000]/mm3
Neu有意が72.2%, Ly有意が20.4%. 他にMo有意やEo有意が少数
Neu, ly同程度の上昇もある
・CSF-Protは132mg/dL[32-857]
正常が4例, 中等度上昇が17例, 高度上昇(>100)が30例
CSF-Gluは正常. 一部で低下する報告もあり
DIAMは基本的に除外診断となる.
・髄液所見の比較(この論文ではリンパ球有意となっているが, そうとも言い難いため注意!)(Drug-induced aseptic meningitis: a mini-review. Fundamental & Clinical Pharmacology 2018)
・また, 原因薬剤中止後数日で改善することも特徴の1つ.
髄液所見や臨床症状は2-3日で改善することが多い
細菌性髄膜炎では7-21日かかる
DIAMの治療は原因薬剤の中止と対症療法
・ステロイドを試す報告もあるが, 有用かどうかは不明.
-------------------------------–
高齢者への無意味なNSAID長期連日処方は ほんと犯罪
疾患によってはやらないといけないことはありますが, その場合は最大限注意しています
フォロー期間とかLabフォローとか云々.
-------------------------------–
高齢者への無意味なNSAID長期連日処方は ほんと犯罪
疾患によってはやらないといけないことはありますが, その場合は最大限注意しています
フォロー期間とかLabフォローとか云々.